いつも当院のホームページをご覧いただき、
ありがとうございます。
今回は、2回目となった公開セミナー「超高齢化社会で生きる私たちの心構え」のレポートを掲載したいと思います。
2回目となった今回は、開催場所をJR鎌倉駅前の生涯学習センターへと移し、金曜日の夜6:30~から行われました。
今回の講師も当院院長の岡田にお願いし、加速度的に進む高齢化社会をテーマに取り上げて、スライドを使用しながらお話しさせていただきました。
我々の病院がある鎌倉市は高齢化率30%という日が、そう遠くない未来にやってきます。
平均寿命が世界1は素晴らしく、誇れることですが、健康寿命を延ばすことがこれからの課題なのではないでしょうか?

次回の講演は、鎌倉市役所内にて認知症をテーマに10月23日に行われます。詳細は近日中に当院ホームページに掲載いたしますので、お時間のある方はぜひ会場へ足を運んでみてはいかがでしょうか?
皆さんのご来場をお待ちしております。
ありがとうございます。
今回は、2回目となった公開セミナー「超高齢化社会で生きる私たちの心構え」のレポートを掲載したいと思います。
2回目となった今回は、開催場所をJR鎌倉駅前の生涯学習センターへと移し、金曜日の夜6:30~から行われました。
今回の講師も当院院長の岡田にお願いし、加速度的に進む高齢化社会をテーマに取り上げて、スライドを使用しながらお話しさせていただきました。
我々の病院がある鎌倉市は高齢化率30%という日が、そう遠くない未来にやってきます。
平均寿命が世界1は素晴らしく、誇れることですが、健康寿命を延ばすことがこれからの課題なのではないでしょうか?

次回の講演は、鎌倉市役所内にて認知症をテーマに10月23日に行われます。詳細は近日中に当院ホームページに掲載いたしますので、お時間のある方はぜひ会場へ足を運んでみてはいかがでしょうか?
皆さんのご来場をお待ちしております。
こんにちは。
医師の木村です。
前回は軽度認知障害について書きましたが、
今回は実際のところ、ど~すれば良いの?・・・ということで、
『予防としての食生活』について触れたいと思います。
いろいろとメディアなどでも取り上げられているので、
同じ内容が重なることもあるかと思いますが、
お付き合いください。
まず、基本として バランスの取れた食事が大切です。
1日3食、色々な食材を腹8分目に摂り、
塩分や動物性脂肪や甘いものを控えめにすることがポイントです。
特に野菜や果物をしっかり摂ると、
認知症のリスクが減少するといった研究もあります。
野菜・果物には、ビタミンC、ビタミンE,β(ベータ)カロテンが多く含まれ、効果的なようです。
ビタミンCは柑橘(かんきつ)類・パプリカ・パセリなどが代表格でしょうか。
β(ベータ)カロテンは、緑黄色野菜に多いといわれています。
また、魚に含まれる“不飽和脂肪酸”は健康だけでなく、
認知機能にも良いといわれており、
魚中心の食事を心がけると、
認知症の予防になるとの報告もあります。
和食が見直されているという話が出るのもうなずけますネ。
![resize[2].jpg resize[2].jpg](http://clinic-1.jp/blog/media/824/resize[2].jpg)
医師の木村です。
前回は軽度認知障害について書きましたが、
今回は実際のところ、ど~すれば良いの?・・・ということで、
『予防としての食生活』について触れたいと思います。
いろいろとメディアなどでも取り上げられているので、
同じ内容が重なることもあるかと思いますが、
お付き合いください。
まず、基本として バランスの取れた食事が大切です。
1日3食、色々な食材を腹8分目に摂り、
塩分や動物性脂肪や甘いものを控えめにすることがポイントです。
特に野菜や果物をしっかり摂ると、
認知症のリスクが減少するといった研究もあります。
野菜・果物には、ビタミンC、ビタミンE,β(ベータ)カロテンが多く含まれ、効果的なようです。
ビタミンCは柑橘(かんきつ)類・パプリカ・パセリなどが代表格でしょうか。
β(ベータ)カロテンは、緑黄色野菜に多いといわれています。
また、魚に含まれる“不飽和脂肪酸”は健康だけでなく、
認知機能にも良いといわれており、
魚中心の食事を心がけると、
認知症の予防になるとの報告もあります。
和食が見直されているという話が出るのもうなずけますネ。
![resize[2].jpg resize[2].jpg](http://clinic-1.jp/blog/media/824/resize[2].jpg)
こんにちは。
医師の木村といいます。
岡田院長→大山副院長とつながれてきたこのブログで、
とうとう私の順番が廻ってきました(笑)
どのような内容が良いのか?
いろいろと考えをめぐらせましたが、
やはり近年避けては通れない「高齢化、認知症」について、
私なりの考えを記してみようと思います。
最近、医療の進歩にともない表題にある「軽度認知症」という言葉が多く使われています。
これは、“もの忘れ、年相応とみるには様子がおかしく、かといって、認知症というほどひどくはなく、日常生活を送っている”といったところでしょうか。
つまり、「健康な状態と認知症の間の段階と考えてください。」とよく言われています。
軽度認知障害の方が、将来認知症になる確率は様々な数字が言われていますが、3割~5割という数字も出ています。
いずれにしても、早期診断で軽度認知障害とわかれば、将来認知症へ移行するのを防げたり、遅らせたりすることができると見解は一致しています。
そのため、少しでもおかしいと思ったら早めの専門外来の受診をお奨めします。
対処法として、場合によって認知症の進行を遅らせる薬を使うこともありますが、ほとんどは食事・運動など生活習慣の見直しをアドバイスし、定期的に病状評価の受診を奨めています。
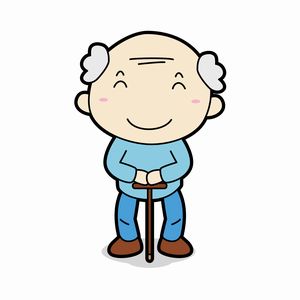
医師の木村といいます。
岡田院長→大山副院長とつながれてきたこのブログで、
とうとう私の順番が廻ってきました(笑)
どのような内容が良いのか?
いろいろと考えをめぐらせましたが、
やはり近年避けては通れない「高齢化、認知症」について、
私なりの考えを記してみようと思います。
最近、医療の進歩にともない表題にある「軽度認知症」という言葉が多く使われています。
これは、“もの忘れ、年相応とみるには様子がおかしく、かといって、認知症というほどひどくはなく、日常生活を送っている”といったところでしょうか。
つまり、「健康な状態と認知症の間の段階と考えてください。」とよく言われています。
軽度認知障害の方が、将来認知症になる確率は様々な数字が言われていますが、3割~5割という数字も出ています。
いずれにしても、早期診断で軽度認知障害とわかれば、将来認知症へ移行するのを防げたり、遅らせたりすることができると見解は一致しています。
そのため、少しでもおかしいと思ったら早めの専門外来の受診をお奨めします。
対処法として、場合によって認知症の進行を遅らせる薬を使うこともありますが、ほとんどは食事・運動など生活習慣の見直しをアドバイスし、定期的に病状評価の受診を奨めています。
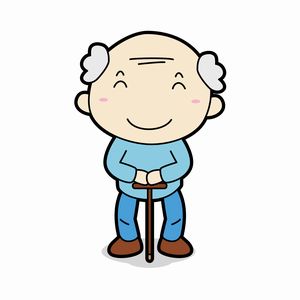
皆さんこんにちは。
今回のブログは、8月3日土曜日に行われた当院としては初めての取り組み、院外セミナーの様子をレポートしたいと思います。
今年の10月に竣工する新棟へ向けて、「新たなスタートを切る年にしていきたい」。
そんな思いで、精神科病院としてだけでなく、本当の意味で地域に根ざすことができる病院を目指していくため、当院では毎月1回の公開セミナーを行うことにしました。
第1回目となる今回は、岡田院長を講師として、当院の成り立ちから現在に至るまでの経緯、現在の工事状況等の話のあと、最近世間を騒がしている「脱法ハーブ」にまで話題は広がっていきました。この時の様子の一部を、ホームページのトップページにあるバナー、YOU TUBEからもご覧いただけます。

このような催しを、毎月1回予定しております。
次回は9月13日金曜日、場所はJR鎌倉駅前にある「鎌倉生涯学習センター 第6集会室」にて、18:30~19:15の予定で行われます。
テーマは、
「超高齢化社会で生きる、私たちの心構え」
です。
急速に進む高齢化社会が叫ばれて久しい昨今。
家族・友人etc。私たちを取り巻く環境の中で、どのようなことを心がけていけば良いのか? この機会に、専門医と一緒に考える時間をつくってみませんか?
皆様のご来場ををお待ちしております。
今回のブログは、8月3日土曜日に行われた当院としては初めての取り組み、院外セミナーの様子をレポートしたいと思います。

今年の10月に竣工する新棟へ向けて、「新たなスタートを切る年にしていきたい」。
そんな思いで、精神科病院としてだけでなく、本当の意味で地域に根ざすことができる病院を目指していくため、当院では毎月1回の公開セミナーを行うことにしました。
第1回目となる今回は、岡田院長を講師として、当院の成り立ちから現在に至るまでの経緯、現在の工事状況等の話のあと、最近世間を騒がしている「脱法ハーブ」にまで話題は広がっていきました。この時の様子の一部を、ホームページのトップページにあるバナー、YOU TUBEからもご覧いただけます。

このような催しを、毎月1回予定しております。
次回は9月13日金曜日、場所はJR鎌倉駅前にある「鎌倉生涯学習センター 第6集会室」にて、18:30~19:15の予定で行われます。
テーマは、
「超高齢化社会で生きる、私たちの心構え」
です。
急速に進む高齢化社会が叫ばれて久しい昨今。
家族・友人etc。私たちを取り巻く環境の中で、どのようなことを心がけていけば良いのか? この機会に、専門医と一緒に考える時間をつくってみませんか?
皆様のご来場ををお待ちしております。
こんにちは、副院長の大山です。
5回目となる今回は、院長の岡田もこのブログで掲載していた「統合失調症」について、私なりの見解を書いてみようと思います。
皆さん、聞いたことはあっても意外とどんな病気か知られていない「統合失調症」。
以前は『精神分裂病』と呼ばれていましたが、病気に対する誤解や偏見を正すため2002年に名称が変更されました。
症状は大きく分けて 「陽性症状」 と 「陰性症状」 に分けられます。
「陽性症状」には、“妄想” “幻覚” “奇異な行動”などがあります。
“妄想”とは、誤った信念のことで、たとえば、被害妄想がある人などは、
「後をつけられている」 「誰かに見張られている」 などと思い込むことがあります。
“幻覚”で最も多いのは幻聴で、「自分の行動に意見を述べる声」 「批判的なことをいう声」 などが聞こえることがあります。
「陰性症状」とは、健康な時の精神状態から何かが欠落したような状態を言います。“意欲低下”や“感情の鈍感化”、“会話の貧困化”などです。症状が重度で、日常生活が困難な時は、入院になることもあります。
発病の原因はまだわかっていませんが、現在では「遺伝と環境原因」の両方が組み合って起こるものと考えられています。
治療法としては精神薬が有効です。そのためには、精神科や心療内科を受診し、症状に応じた処方を受けてください。
現在は薬も進歩し、有効率もずいぶん高まってきました。
治療後に回復した後は、再発再燃を防ぐために継続的に服用するのが理想的です。
さて、5回にわたって精神的な病気に対する、私なりの見解を書いてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか?
当林間病院には、院長と私以外にも、精神保健指定医の常勤医師があと2名在籍しています。ここで、皆さんの健康をお祈りしつつ、次の医師にバトンを渡したいと思います。
乱文、失礼いたしました。
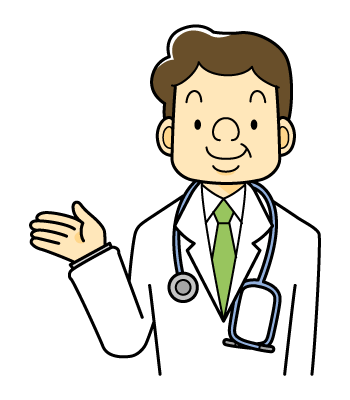
5回目となる今回は、院長の岡田もこのブログで掲載していた「統合失調症」について、私なりの見解を書いてみようと思います。
皆さん、聞いたことはあっても意外とどんな病気か知られていない「統合失調症」。
以前は『精神分裂病』と呼ばれていましたが、病気に対する誤解や偏見を正すため2002年に名称が変更されました。
症状は大きく分けて 「陽性症状」 と 「陰性症状」 に分けられます。
「陽性症状」には、“妄想” “幻覚” “奇異な行動”などがあります。
“妄想”とは、誤った信念のことで、たとえば、被害妄想がある人などは、
「後をつけられている」 「誰かに見張られている」 などと思い込むことがあります。
“幻覚”で最も多いのは幻聴で、「自分の行動に意見を述べる声」 「批判的なことをいう声」 などが聞こえることがあります。
「陰性症状」とは、健康な時の精神状態から何かが欠落したような状態を言います。“意欲低下”や“感情の鈍感化”、“会話の貧困化”などです。症状が重度で、日常生活が困難な時は、入院になることもあります。
発病の原因はまだわかっていませんが、現在では「遺伝と環境原因」の両方が組み合って起こるものと考えられています。
治療法としては精神薬が有効です。そのためには、精神科や心療内科を受診し、症状に応じた処方を受けてください。
現在は薬も進歩し、有効率もずいぶん高まってきました。
治療後に回復した後は、再発再燃を防ぐために継続的に服用するのが理想的です。
さて、5回にわたって精神的な病気に対する、私なりの見解を書いてみましたが、皆さんいかがだったでしょうか?
当林間病院には、院長と私以外にも、精神保健指定医の常勤医師があと2名在籍しています。ここで、皆さんの健康をお祈りしつつ、次の医師にバトンを渡したいと思います。
乱文、失礼いたしました。
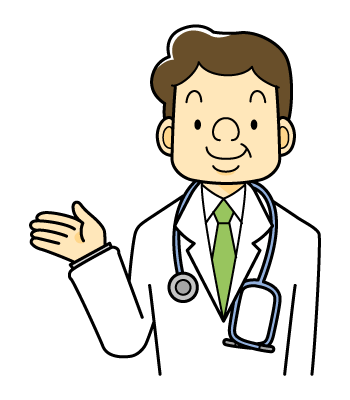
こんにちは。
副院長の大山です。
前回の「認知症との向き合い方」につづく、
2回目の今回は、
「認知症と介護サービスについて」の話をしようと思います。
実際に、高齢化社会に伴い、認知症が増えてきていることは否めません。
そして、発症しても本人に自覚がない場合がほとんどです。
家族から見て、著しい物忘れなどの認知症を疑う症状があったら、
早めに医療機関を受診しましょう。
医療機関では、診察・必要な検査を行い、診断します。
『同じものばかりをたくさん買ってくる』
『事実と異なることを、当然のように話す』
など、家族からの客観的な情報は、診察の際重要な情報になります。
認知症と思われていたのに、実は他の病気(うつや脳こうそくなど)だった・・・
なんていうこともあります。
現在の医療では、認知症を回復させることはできません。
認知症と診断されたら更なる悪化を避け、現状を保っていくことが目標となります。
認知症の程度によっては、生活のサポート・介護支援が必要です。
そのためには、市役所で介護保険を申請し、介護サービスを活用することをお勧めします。
認知症は進行すると、介護負担が大きくなり家族のみで対応することが困難となってきます。本人と家族、双方のためにも介護サービスを上手に利用して下さい。
最後に。
物忘れ以外の、妄想や徘徊といった症状が目立つ場合は専門医の受診をお勧めします。お薬を使うことで、症状が軽減できる場合がほとんどです。そうして症状が安定した後に、適切な介護サービスを受けると良いでしょう。

副院長の大山です。
前回の「認知症との向き合い方」につづく、
2回目の今回は、
「認知症と介護サービスについて」の話をしようと思います。
実際に、高齢化社会に伴い、認知症が増えてきていることは否めません。
そして、発症しても本人に自覚がない場合がほとんどです。
家族から見て、著しい物忘れなどの認知症を疑う症状があったら、
早めに医療機関を受診しましょう。
医療機関では、診察・必要な検査を行い、診断します。
『同じものばかりをたくさん買ってくる』
『事実と異なることを、当然のように話す』
など、家族からの客観的な情報は、診察の際重要な情報になります。
認知症と思われていたのに、実は他の病気(うつや脳こうそくなど)だった・・・
なんていうこともあります。
現在の医療では、認知症を回復させることはできません。
認知症と診断されたら更なる悪化を避け、現状を保っていくことが目標となります。
認知症の程度によっては、生活のサポート・介護支援が必要です。
そのためには、市役所で介護保険を申請し、介護サービスを活用することをお勧めします。
認知症は進行すると、介護負担が大きくなり家族のみで対応することが困難となってきます。本人と家族、双方のためにも介護サービスを上手に利用して下さい。
最後に。
物忘れ以外の、妄想や徘徊といった症状が目立つ場合は専門医の受診をお勧めします。お薬を使うことで、症状が軽減できる場合がほとんどです。そうして症状が安定した後に、適切な介護サービスを受けると良いでしょう。

今回のブログは、先日院内にて行われた患者さん向けの音楽会の模様をアップします。
演奏は、ヴァイオリン=岡田院長、ピアノ=黒田理事の豪華セッションとなっています。
皆さん、お楽しみください。
演奏は、ヴァイオリン=岡田院長、ピアノ=黒田理事の豪華セッションとなっています。
皆さん、お楽しみください。
こんにちは。
副院長の大山です。
今回は、2回にわたって「認知症」の話をしようと思います。
皆さんご存知のように、高齢化社会に突入した日本。
誰でも年をとることで、多少の物忘れは出現します。
大まかに言うと・・・
1.「内容は思い出せないけど、忘れたことは分かっている」
2.「忘れたことすらわかっていない」
上記のうち、
1.は『単なる物忘れ』
2.は『認知症』
と大雑把に分けることができます。
認知症は、2.に加え妄想で「財布を取られた」など事実と異なることを訴えたり、「季節外れの服装をする」など判断力低下を思わせる言動が見られることもあります。
こんな時、認知症から起こるちぐはぐは行動に家族が腹を立ててはいけません。なぜなら判断力が低下しても感情は伝わり、怒られていることのみを実感してしまうからです。
認知症は脳の障害や衰えから発症する病気のため、専門機関としては精神科や神経内科を受診するのが良いでしょう。また、認知症は進行性なので早期発見・対応で症状の悪化を抑えられる場合があります。
診察するうえでは、家族から得られる「普段の情報」が重要です。
受診の際は、ご一緒されることをお勧めします。

副院長の大山です。
今回は、2回にわたって「認知症」の話をしようと思います。
皆さんご存知のように、高齢化社会に突入した日本。
誰でも年をとることで、多少の物忘れは出現します。
大まかに言うと・・・
1.「内容は思い出せないけど、忘れたことは分かっている」
2.「忘れたことすらわかっていない」
上記のうち、
1.は『単なる物忘れ』
2.は『認知症』
と大雑把に分けることができます。
認知症は、2.に加え妄想で「財布を取られた」など事実と異なることを訴えたり、「季節外れの服装をする」など判断力低下を思わせる言動が見られることもあります。
こんな時、認知症から起こるちぐはぐは行動に家族が腹を立ててはいけません。なぜなら判断力が低下しても感情は伝わり、怒られていることのみを実感してしまうからです。
認知症は脳の障害や衰えから発症する病気のため、専門機関としては精神科や神経内科を受診するのが良いでしょう。また、認知症は進行性なので早期発見・対応で症状の悪化を抑えられる場合があります。
診察するうえでは、家族から得られる「普段の情報」が重要です。
受診の際は、ご一緒されることをお勧めします。

こんにちは。
副院長の大山です。
今日は睡眠の話をしようと思います。
これから暑くなると、寝苦しい日が続きそうですね。
人生の3分の1を占めるといわれる睡眠。
その睡眠が十分にとれない“不眠症”の症状や治療についてのお話です。
症状
大きく3つに分けられます
『寝つきが悪い(入眠困難)』
『夜中に何度も起きてしまう(中途覚醒)』
『朝早くから起きてしまう(早朝覚醒)』
以上のような状態で困っていることを不眠症と言います。
また、睡眠の時間だけでなく、眠りの質が問題になることもあります。
原因
これについては、緊張や不安による精神の高ぶり、
不規則な生活や加齢などです。
また、お酒の飲みすぎは眠くなるので一見良さそうですが、
中途覚醒・早朝覚醒を起こしてしまうので注意しましょう。
改善方法
まずは『規則正しい生活』を。
前夜にあまり眠れなくても朝はしっかり起きて、光を浴びます。
適度な運動も効果的でしょう。
また、眠る環境を整えることも大切なので、
温度や湿度調整などで工夫を。
寝る前にゆったりとした音楽を聴くことや、
温かい飲み物でリラックスすることも有効です。
日中の生活環境の改善は、眠りの質も向上させます。
最後に
睡眠薬の使用については、市販のものもありますが、
症状が続く場合は専門医への相談をお勧めします。
うつ病や身体疾患から起こる不眠もあるので、
受診をして適切な薬を処方してもらいましょう。
現在の睡眠薬は用法・用量を守れば、生活への支障もありません。
しっかりと睡眠をとって、暑い夏を乗り切りましょう。

副院長の大山です。
今日は睡眠の話をしようと思います。
これから暑くなると、寝苦しい日が続きそうですね。
人生の3分の1を占めるといわれる睡眠。
その睡眠が十分にとれない“不眠症”の症状や治療についてのお話です。
症状
大きく3つに分けられます
『寝つきが悪い(入眠困難)』
『夜中に何度も起きてしまう(中途覚醒)』
『朝早くから起きてしまう(早朝覚醒)』
以上のような状態で困っていることを不眠症と言います。
また、睡眠の時間だけでなく、眠りの質が問題になることもあります。
原因
これについては、緊張や不安による精神の高ぶり、
不規則な生活や加齢などです。
また、お酒の飲みすぎは眠くなるので一見良さそうですが、
中途覚醒・早朝覚醒を起こしてしまうので注意しましょう。
改善方法
まずは『規則正しい生活』を。
前夜にあまり眠れなくても朝はしっかり起きて、光を浴びます。
適度な運動も効果的でしょう。
また、眠る環境を整えることも大切なので、
温度や湿度調整などで工夫を。
寝る前にゆったりとした音楽を聴くことや、
温かい飲み物でリラックスすることも有効です。
日中の生活環境の改善は、眠りの質も向上させます。
最後に
睡眠薬の使用については、市販のものもありますが、
症状が続く場合は専門医への相談をお勧めします。
うつ病や身体疾患から起こる不眠もあるので、
受診をして適切な薬を処方してもらいましょう。
現在の睡眠薬は用法・用量を守れば、生活への支障もありません。
しっかりと睡眠をとって、暑い夏を乗り切りましょう。

こんにちは。
副院長の大山といいます。
岡田院長からのバトンをもらい、
今回から数回、記事を書いてみようと思います。
最初となる今回は、題名の通り。
他の病気と同様に、心の病気が始まるときにも何らかの変化が現れます。
身近に接している家族や友人が、一番最初の“ドクター”です。
その人の状態が普段と変わってきたとき、
我々は心の病気も疑います。
『気分が落ち込む』 『意欲がわかない』 『人に会うのが怖い』
などの精神症状が主ですが、
身体症状(胃痛や高血圧、円形脱毛症など)として現れる場合もあります。
心の病気を疑ったら、規則正しい生活を基本に、
趣味など自分の楽しめるものでリラックスを。
思っていることは言葉に出すだけでも、
思いのほか楽になる場合もあります。
ただ、本人自身ではよくわからないこともあるので、
周りの人がいち早く異常や変化に気づくことが大事です。
早期発見・対応により症状の悪化を食い止め、
回復させることだって可能です。
本人の言葉にキチンと耳を傾け、
気をかけてあげてください。
周りの人によるケアはもちろん、
症状に適した治療のためには専門医の治療・助言も重要です。
適切な対応・治療で早期回復し、健やかな毎日を送ってください。

副院長の大山といいます。
岡田院長からのバトンをもらい、
今回から数回、記事を書いてみようと思います。
最初となる今回は、題名の通り。
他の病気と同様に、心の病気が始まるときにも何らかの変化が現れます。
身近に接している家族や友人が、一番最初の“ドクター”です。
その人の状態が普段と変わってきたとき、
我々は心の病気も疑います。
『気分が落ち込む』 『意欲がわかない』 『人に会うのが怖い』
などの精神症状が主ですが、
身体症状(胃痛や高血圧、円形脱毛症など)として現れる場合もあります。
心の病気を疑ったら、規則正しい生活を基本に、
趣味など自分の楽しめるものでリラックスを。
思っていることは言葉に出すだけでも、
思いのほか楽になる場合もあります。
ただ、本人自身ではよくわからないこともあるので、
周りの人がいち早く異常や変化に気づくことが大事です。
早期発見・対応により症状の悪化を食い止め、
回復させることだって可能です。
本人の言葉にキチンと耳を傾け、
気をかけてあげてください。
周りの人によるケアはもちろん、
症状に適した治療のためには専門医の治療・助言も重要です。
適切な対応・治療で早期回復し、健やかな毎日を送ってください。
