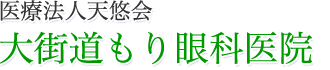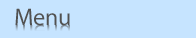こどもの視力
視力の発達過程や遠視・近視・乱視等の屈折異常の発達について、幾多の理論がありますが、
一般的に述べられていることを参考までに取り上げてみました。
視覚の発達過程
生まれたばかりの新生児の眼の大きさは直径約17.5mmで、これが3歳までに22.5mmとなり、成人で24.0mmになる。眼の発育は脳の発育と平行する(眼は脳の一部)と考えられている。生まれたばかりの乳児でも視神経はかなり発達しており、光に対する生理的反応は乳児でも大人でもそれほど変わりはない。しかし、それが大脳に達して視覚パターンを形成し、認識をするという点になると、乳幼児と成人では大分異なっている。 生まれたばかりのときには目的のない眼球運動を行い、凝視したり動くものを追ったりする能力は発達してない。そのうち突然眼に入る光を見つめたり瞬きをし、しばらくの間じっと注視するとか、身体の運動を止めることがある。はじめは片眼・片眼を使っており、両眼の共働運動は発達していない。両眼視は6週間頃に発達し始め、6ヶ月でよく確立し、生後1年では両眼の統合は完全なものとなるといわれている。
それでは、視力の発達(片眼ずつの見えたか)について詳しく調べてみると、生後1ヶ月では光を感ずる(光覚)程度であり、2ヶ月で眼前に動くものに反応(手動弁)でき、4ヶ月で視力0.02、6ヶ月で0.06程度の発達であるという研究報告がある。その後、1歳児で0.2、2歳児で0.5程度に発達し、満6歳で1.0となり視力はほぼ完成に近い視力が得られ、8~9歳で視機能の発達はほぼ完了すると考えられている。
この発達に不可欠なものが「視性刺激」といわれる、網膜中心窩にピントのあった像が精確に映るようにすることです。 視力の発達時期に、「視性刺激」が何らかの原因で遮断されることによって、視力の発達がストップしてしまったものを、「弱視」といいます。この場合は、成人になってメガネやコンタクトレンズを装用しても視力を確保することが困難となります。
こどものメガネ
普通、乳児の屈折度は+2.00D前後の遠視です。成長に伴い、7歳頃までは遠視がやや増加する傾向にあり、それ以後は急速に正視化します。こどもの屈折の状態は、「眼軸長」、「角膜曲率」、「水晶体の屈折度」のバランスによって常に変化しております。
1. 不同視とメガネ
一般に左右の屈折差が2.00D以上の不同視の場合、屈折が遠視側に一眼が弱視になる可能性があります。場合によっては「健眼遮蔽法」によって弱視眼に視性刺激を与え視機能訓練をすることが必要です。
2. 遠視とメガネ
両眼が+4.00~+5.00D以上の遠視の場合、両眼ともピント合わせが困難なため両眼の弱視になることがあります。さらに、+3.00D以上の場合、調節に伴う輻輳のため、調節性内斜視を合併することがありますので注意が必要です。これらは完全屈折矯正の眼鏡処方の適用とし、調節麻痺剤点眼後(サイプレジン、アトロピン)のオートレフの値のメガネを装用し、精確な「視性刺激」を常に与え続け視機能の発達を促進させます。斜視がなく遠視の程度が軽いほど予後がよく、治療に反応しやすいようです。
3. 近視とメガネ
普通、近視の場合は近距離にピントが合いやすいので、比較的弱視にはなりにくいが、-2.00D~-3.00D以上の近視がある場合は十分注意します。必要に応じてやや弱めのメガネを処方します。
4. 乱視とメガネ
2.00D以上の乱視がある場合は、「経線弱視」を引き起こす可能性があるのでメガネが必要です。
調節緊張とメガネ】(仮性近視、学校近視、偽近視)
戸外遊びが少なく、室内での勉強や塾通い、テレビ鑑賞やテレビゲーム等々、眼前1m以内での長時間の作業を続けることによって、眼の調節を司る毛様体筋が過度の緊張を強いられ柔軟性を失ってしまうことがあります。このため調節痙攣や調節緊張を起こし、調節力が乏しい遠くが見えにくい「近視」と同じ状態が生じることがあります。これを仮性近視といい、早期で調節力の回復がはかられる場合には視力の回復が可能となりますが、時機を失するとこどもなのに「老眼」のような状態になったり、眼軸長が伸びてしまい「真性近視(軸性近視)」に変化してしまうことがあると云われております。近視になるメカニズムは諸説があり、まだ、解明されておりませんが、少なくとも長時間の近方作業は、視力の回復を阻害します。また、このような状態で、正しい眼の屈折と調節の状態を把握してから、メガネを装用しないと、いわゆる「近視が進む」ことになりかねません。人間の情報の約90%は眼から入ると云われております。自分の眼の状況を正しく把握することは、正しい情報を得ることに繋がります。